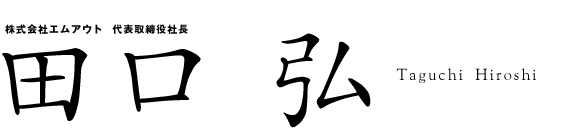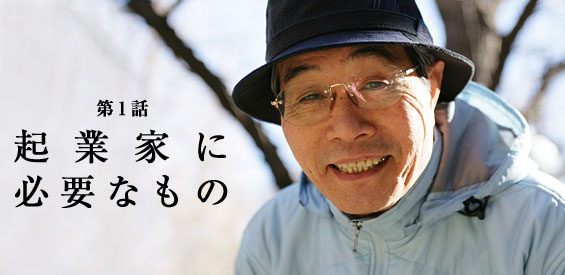大学卒業後、農機具会社(大竹農機、現・大竹製作所)で営業をやっていた時期がありました。大学(愛知学院大学)時代のゼミの教授から紹介を受けて行ったという、実に主体性のない話でしてね。地方の農機具屋や農業協同組合を回ったりしていました。
大学卒業後、農機具会社(大竹農機、現・大竹製作所)で営業をやっていた時期がありました。大学(愛知学院大学)時代のゼミの教授から紹介を受けて行ったという、実に主体性のない話でしてね。地方の農機具屋や農業協同組合を回ったりしていました。
何もわからないままに、全自動の脱穀機を売って歩いていたんですよ。でも地方回りがおもしろくて楽しくやっていました。地方で開催される展示会などに行くと、同業者がみんな集まってきて、そういう連中と一緒に泊まって遊んだりして。長崎、秋田、鳥取と、ずいぶんいろいろなところへ行かせてもらいました。
約4年間在籍しましたが、そこで気がついたのは、やはり自分は営業には向いていないなということでした。元来、酒が飲めないので、農協などに行くと酒が飲めないと買ってもらえなくて、無理してたいへんな思いをしたこともありました。人間関係のしがらみや、酒を酌み交わしながら物を売っていくというのはあんまり得手じゃないということがよくわかりました。
僕はその農機具会社で一時期東京営業所にいたのですが、本社のある名古屋へ帰っていたんです。ところがその東京時代の友人たちから、新しい会社を作るから一緒にやらないかと声をかけられまして。僕自身ももう一度東京へ出て行き、何か新しいことをやってみたいという気持ちもありましたからね。
それが三住商事(現・ミスミグループ本社)という会社です。東京時代の友人は高校の同級生でもありまして、3人で始めて最初は友人のひとりが社長をやっていました。
最初は、高周波を使った自動水洗器を売る販売会社として始まったのです。ところがその商品が不良品であることがわかりましてね。そもそも、技術的に無理なものだったんです。保健所から推薦をもらったりして、明治記念館をはじめいろいろなところに設置して歩いたんです。ところが水が出っ放しになって全然とまらないとか、逆に水が出ないとか、そういうトラブルが続出して。
 結局その商品を売るためにと思って作った会社ですが、肝心の商品がだめになってしまったわけで、やることがなくなってしまったわけですよ。それでも、何かで飯を食わなければいけないということで、いろいろなことをやってみたわけです。創立メンバーのひとりがかつてベアリングの商社にいたので、じゃあベアリングを売ろうと仕入れて売りはじめました。
結局その商品を売るためにと思って作った会社ですが、肝心の商品がだめになってしまったわけで、やることがなくなってしまったわけですよ。それでも、何かで飯を食わなければいけないということで、いろいろなことをやってみたわけです。創立メンバーのひとりがかつてベアリングの商社にいたので、じゃあベアリングを売ろうと仕入れて売りはじめました。
僕もその仕事を一緒にやっていたんです。ベアリングはボールが入ったものが一般的ですが、ボールではなくて、巾の広いニードルローラーが入ってるベアリングがありまして、お客さんの中からこのニードルローラーだけ売ってくれっていう注文がちょくちょくあったんですね。そこで、これはいったい何に使うんでしょうかと尋ねてみたところ、金型用のロックピン代わりにするんだと教えてもらえました。実は当時そういう部品は日本にはなくて米国から取り寄せていたそうなんです。であれば、それを作ってみようじゃないか、ということではじまったのが、現在のミスミのベースになっている金型用の標準部品なのです。
売る物がなくなったためにどうしようかということで、お客様に、今、何に困っているんですか。何が欲しいんですか、と聞いて商売をやりはじめた。それが、生産者の販売代理店ではなくて、消費者の購買代理店、つまりプロダクトアウトからマーケットアウトに発展してきたということでしょうね。
 当時の機械工具商というものは、ほとんどがメーカーの販売代理店だったんですね。それに対して、ユーザーの購買代理店をやろうと思い立ったわけです。そもそもわが国の産業構造っていうのはすべからく物不足時代にできた仕組みなんですね。だから、物を作ることが最優先しているわけです。そこから発展していって、供給側の論理であらゆる商売というものができあがっているのです。それを消費者側の論理に変えていこう、というのがマーケットアウトの基本となる考え方ですね。
当時の機械工具商というものは、ほとんどがメーカーの販売代理店だったんですね。それに対して、ユーザーの購買代理店をやろうと思い立ったわけです。そもそもわが国の産業構造っていうのはすべからく物不足時代にできた仕組みなんですね。だから、物を作ることが最優先しているわけです。そこから発展していって、供給側の論理であらゆる商売というものができあがっているのです。それを消費者側の論理に変えていこう、というのがマーケットアウトの基本となる考え方ですね。
僕が学生時代を送った1950年代から60年代は流通革命の時代なんですね。関西ではダイエーの中内(功)さんが立ち上げた主婦の店「ダイエー」、東京・北千住ではイトーヨーカドーの伊藤(雅俊)さんの洋品店「羊華堂」、四日市では今のイオングループの岡田(卓也)さんの呉服屋「岡田屋」といった会社が、この流通革命の波に乗って大変な勢いで伸びていき、これらを目の当たりにしたことで、ずいぶん勉強させていただきました。
そもそも購買代理店という発想は、当時ベストセラーになった東京大学の林周二先生が書かれた『流通革命論』(中公新書)の中にすでに登場していたものなのです。ただ、あくまでも当時の流通革命は消費財におけるものであって、購買代理店そのものは日の目を見なかったのです。
 僕がはじめた購買代理店の仕組みは生産財の市場においてだったわけです。あくまでもビジネスのニーズに基づいて商品を作っていく。ところが、消費財というものは理論どおりにはいかないものなんですよ。だって、好き嫌いの問題で、非常に情緒的な世界ですからね。一方、生産財は需要や数字がはっきり見てくるもので、理論どおりいくものですから、購買代理店の仕組みが非常にすんなり受け入れられたのでしょうね。
僕がはじめた購買代理店の仕組みは生産財の市場においてだったわけです。あくまでもビジネスのニーズに基づいて商品を作っていく。ところが、消費財というものは理論どおりにはいかないものなんですよ。だって、好き嫌いの問題で、非常に情緒的な世界ですからね。一方、生産財は需要や数字がはっきり見てくるもので、理論どおりいくものですから、購買代理店の仕組みが非常にすんなり受け入れられたのでしょうね。
プロダクトアウトというのは生産者側に主張があって、それがマーケット側に対して主張しているということなんですね。ところが、マーケットアウトというのはマーケットの意見に基づいてビジネスを行うものですから、言ってみれば自己主張のないビジネスなんですね。
東洋経済新報社の梅沢(正邦)さんは僕の経営を「空の経営」とおっしゃっています。自己主張をするのではなくて、自分を「無」にしてお客様のニーズに基づいてビジネスをする。子供時分から親についてお寺に説教を聞きにいったり、社会人になってからも座禅を組みにいったりしていましたからね。