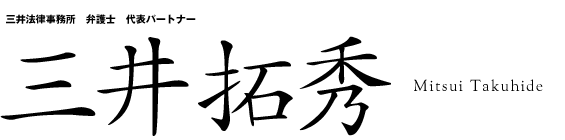なぜ弁護士という職業を選んだのかよく聞かれるのですが、子供の頃から憧れをもっていて、ずっとなりたかったというわけではないですね。親類関係で弁護士をやっている人もいませんでしたし。
自分自身の指向として、大きな組織に入って仕事をするのは嫌だなという思いはありました。子供の頃から会社や役所に勤めている親や親類を見ながら、ずっと言い聞かされてきたのが「すまじきものは宮仕え」ということでした。幼心に、そういうものがすり込まれていたのかもしれません。ですから大学に入るぐらいの頃からでしょうか、どこかの有名な保険会社に行きましょうとか、銀行に行きましょうとか、そういった考えは頭の中にありませんでしたね。
弁護士という職業を知ったのは、小学校の頃です。当時住んでいた家の前に弁護士さんの家がありました。その頃はテレビがまだ珍しい時代でしたが、その家に行くとテレビがあったり、冷蔵庫があったりするわけです。それで弁護士というのは豊かな生活ができる職業なんだなと思いました。
 私の父親は軍人で戦後は防衛庁に勤めていました。いわゆるキャリアシステムの中では恵まれなかった人です。母親は、そんな父を見て意気地がないと思ったのか、学費稼ぎを名目にして自分で商売を始めました。
私の父親は軍人で戦後は防衛庁に勤めていました。いわゆるキャリアシステムの中では恵まれなかった人です。母親は、そんな父を見て意気地がないと思ったのか、学費稼ぎを名目にして自分で商売を始めました。
最初に母のやった仕事というのが不動産業でした。この仕事というのがトラブルが多かった。たとえば誰かに土地を売ったりすると、「最初に俺が声をかけた」とか「俺が紹介したんだ」などという人が次々出てきて、「手数料をよこせ」と始めるわけです。その問題がこじれてくると裁判になったりする。また周りの人から見れば「女だてらに」という思いもあったのでしょう、怒鳴り込まれたり、弱いものいじめをされたりしました。
大学に入ると宅建(宅地建物取引主任者)の資格を取り、母の仕事を手伝うようになりました。そういうトラブルをより間近で見るようになり、反撃できないことが歯がゆかった。なんとか反撃できるような力を持ちたいとよく思ったものです。
母はその後、不動産屋を辞めて別の方と一緒に印刷会社を始めたのですが、私もその仕事を手伝って紙を運搬したり、広告代理店に原稿をもらいにいったりしました。広告や印刷の世界というのは、担当にいくらかキックバックすると仕事を取りやすくなるということがありました。学生の頃からそういう実態を見て、「将来こういう仕事はしたくないな」と思っていました。
大学入学当時は学園紛争が吹き荒れていて、講義がありませんでした。それで母の仕事を手伝っていたというわけです。ゲバ棒を振り回す連中を横目で見ながら、「お前らそんなこと言ってるけど、世の中は違うんだぞ」などと思っていましたよ。
我々団塊の世代には共通かなと思いますけれど、子供の頃から海外への志、とくに米国へのあこがれが強くありました。山本一力さんの小説で『ワシントンハイツの旋風』というのがありますけれど、まさにあの小説で書かれた時代の雰囲気とでもいうのでしょうか。
弁護士の仕事がいいなと本格的に思うようになったのは、大学に入学してからです。日本の金融市場の規制緩和が進んで、それに伴って弁護士が海外に渡って仕事をするということが増えていったのです。私の母方の叔父が役人をしていて海外に留学して、その話を私にしてくれたのです。私は「これはいい」と思いました。"弁護士の道に進んでみよう"と思ったわけです。
大学には6年間通いました。司法試験のために2年間留年しています。6年目で司法試験に受かりました。司法試験の勉強をしている途中に、迷った時期もありました。母親がそんな私を見て「うちの仕事など手伝わずに勉強しなさい」と言い始めた頃、3度目の挑戦で司法試験に合格しました。
合格はしたものの、選択肢がある中で、自分がどのようにすれば早くスキルを身につけることができるのか悩んだものです。丁稚奉公でもいいからと思い当時日本で一番大きな法律事務所の門を叩いたのです。日本一大きいといっても総勢17人しかいませんでした。
そこは企業法務を専門にしていました。法律事務所にお客様である証券会社の方から「こういう取引ができたからこれを契約書にしてほしい」とか、「こういう取引をするのだが、これは法律的にどうなのだろうか」という相談がよくありました。実際のビジネスの現場では、お客様は駆け引きをしたり同業者を出し抜いたりいろいろなことをしているわけで、その法律的な面について相談されるわけです。証券や金融などといった仕事は今まで体験してきた生活ともかけ離れた世界で、商売のやりとりが今ひとつよくわからなかった。本当の商売の肝や勘所、リスクといったものが見えてこないわけです。
 そんなところで「証券取引法第何条によれば」などと言っていてもしょうがない。実際の商売には間に合わないということもありました。それで"現場を見たい"と痛切に感じるようになったのです。それは私の家が商売を手伝っていたとことと関係があると思います。実際の現場ではさまざまなことが起こるものだということを実感していましたから。
そんなところで「証券取引法第何条によれば」などと言っていてもしょうがない。実際の商売には間に合わないということもありました。それで"現場を見たい"と痛切に感じるようになったのです。それは私の家が商売を手伝っていたとことと関係があると思います。実際の現場ではさまざまなことが起こるものだということを実感していましたから。
また私が弁護士になった70年代の後半は、日本の金融関係の市場が規制緩和で沸いていた頃です。お金が日本にどんどん入ってきていました。しかしそうした分野で目立った活躍をしている弁護士は、ほとんど海外の人たちで、日本人はほとんどいませんでした。
日本企業の取引なのに、実際に仕切っているのは米国の証券会社であったり、ロンドンから来る弁護士だったりするわけです。それを見て、取引の大本があるのは海外なのだなと実感したわけです。そういうところを自分の目で見たい。本場の法律や制度を理解したいと思うようになりました。弁護士になってから5年目ぐらいたったころでした。
本来ならその事務所に勤め続けて、キャリアを積んで上へ上がっていけばよかったのでしょうが、心の中では、ニューヨークやロンドンに行ってみたい、さらに違った経験を積んでみたいという思いが募っていったのです。