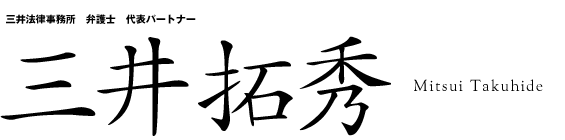ロンドンの東京銀行で1年近く働いたあと、帰国することにしました。私はロンドンで学んだ仕事、具体的には東京銀行で手がけていたデリバティブ取引に関する法務などを手がけようと思っていました。こうした仕事は、当時の日本ではできる弁護士がまだ少ない状況でした。正直、あまり効率のいい仕事というわけではなかったので、手つかずという状態だったのです。それで私自身が金融機関に勤務していたというのを武器に、積極的に銀行に飛び込んでいきました。
1980年代にはデリバティブといっても日本の金融機関にはあまり知られていませんでした。これは日本が知らなかっただけで、海外市場ではずっと昔から行われていたものです。それが規制緩和もあって1990年代には、このデリバティブ取引やスワップ取引が、日本の金融機関にとって積極的に取り組まざるを得ない仕事になってきたわけです。
また、それまでは銀証分離といって銀行と証券は、お互いの壁を乗り越えないということでやって来ていたのですが、だんだんその壁も低くなってきた。銀行が証券会社をつくって、証券業務に積極的に進出するようになったわけです。こうした状況もあって銀行からも証券会社からも次々と依頼が舞い込むようになってきました。
 1986年に設立した事務所というのは私たちをコーディネートしてくれた方の看板を借りて仕事をするという形でした。当時は私たちの名前は出ていませんでした。1988年にはその方からも独立して、三井安田法律事務所を設立することになりました。独立したのは折しもバブルの全盛時代でした。これも運ですね。これから来るぞという思いはなかったのですが、マーケットは沸騰状態になりました。設立した弁護士事務所もどんどん大きくなりました。
1986年に設立した事務所というのは私たちをコーディネートしてくれた方の看板を借りて仕事をするという形でした。当時は私たちの名前は出ていませんでした。1988年にはその方からも独立して、三井安田法律事務所を設立することになりました。独立したのは折しもバブルの全盛時代でした。これも運ですね。これから来るぞという思いはなかったのですが、マーケットは沸騰状態になりました。設立した弁護士事務所もどんどん大きくなりました。
三井安田法律事務所は最盛期で、弁護士が75人ぐらい所属していました。当時はより多く集めれば良いだろう、大きくしなければいけないのだという考えに取り憑かれていてとにかく人数を集めました。しかし、仕事をしている中で、ふと、それは間違いではないかと気が付いたのです。それが今の事務所を設立する転機になりました。
なぜ大きな組織に疑問を感じたのかといいますと、まず時間がかかるというのがありました。弁護士事務所というのはパートナーシップですから、ことにあたるにはパートナーの全員にはからなければならないのです。少人数でやっているうちはいいのですが、ニーズに応えて人数を増やしていくと、全員の了解を得るためにどんどん時間がかかるようになっていくわけです。組織として動きが遅くなっていくのです。
そこで、三井安田法律事務所を解散して、2004年に三井法律事務所を作りました。仕事はこれまでと同様に企業、金融分野に特化した事務所で、現在15人の弁護士がいます。メンバーは以前に比べるとずいぶんと少なくなりました。しかし、この分野に取り組むには不足がないという意識からスタートを決断しました。
こうした気持ちになったのは、私自身が東京銀行に勤務して弁護士を使う立場、顧客の立場に立った経験が大きく作用していると思います。お客様のほうから弁護士事務所を見ると、"大きな事務所に頼めば安心"という面は確かにあるかもしれません。しかし、これは実際のサービスとはあまり関係ありません。たとえば小さい事務所でも「この人に相談したい」という人がいる事務所のほうがありがたかったりするわけです。結局、相談したい弁護士というのは少数でしかないというのが実態です。
また、人数が100人いる法律事務所でも、全員が一つの取引に取り組むということは実際にはありません。現在、大勢の弁護士が必要になる仕事というとM&Aやその相談業務でしょうが、本当に重要な判断をしているのは1人か2人ですし、人数が必要なのは時間をシェアするためという要素が強いからです。それに、たくさんの弁護士が集まって、みんなで討議すれば正しい回答が出てくるというものでもないですからね。
もう一つ、私自身が独立の際に考えたのは、"チーム全員が見渡せる"ということでした。いくらインターネットのような情報伝達手段が普及しても、最後は人と人との肌のふれあいが感じられる、そうしたものや関係をチームとして大切にしたかったということです。
 私が弁護士を使う立場に立って感じたことは「弁護士というのは使いにくい」ということでした。たとえば朝一番で仕事の電話をしてもいない。大事な相談をしようと思っているのに遅刻してくる。本人にすれば「昨日徹夜をしたから」などいろいろな言い訳はあるのでしょうが。
私が弁護士を使う立場に立って感じたことは「弁護士というのは使いにくい」ということでした。たとえば朝一番で仕事の電話をしてもいない。大事な相談をしようと思っているのに遅刻してくる。本人にすれば「昨日徹夜をしたから」などいろいろな言い訳はあるのでしょうが。
弁護士というものは、ただ資格を持っているだけで、偉いわけでも何でもないと思っています。お客様との関係では一般の社会人同士として良い関係を作る必要がありますし、それに必要なのはサービスだと思っています。たとえば、どういうサービスが気が利いているのか、回答はどういうタイミングで投げたらいいのか、請求書を出すタイミングもありますね。そんなことを考えることが実はユーザーにとって大切だと実感していました。
実はそうしたことまで考えてできる弁護士というのは限られていると思います。これは弁護士という資格制度に問題があるのかもしれないですね。試験に受かって弁護士になるわけですが、それだけで、あとは普通のビジネスを知ってるわけでもない、ビジネスのセンスを持っているわけでもないですからね。
あとお客様と弁護士の波長というか相性もありますね。今うちの事務所にやってくるお客様というのは、基本的には「ご紹介」というベースがほとんどです。ですから「テレビで名前を見たから頼みますよ」という人々のお仕事はお断りすることにしています。