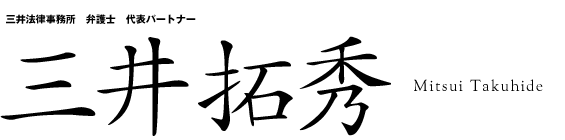弁護士の仕事というものは、すべての答えが六法全書に書かれていると思っている人がいます。しかし、実はそうではありません。六法全書に通暁していて、公になっている判例とか解釈は知っている、しかし、そうした知識のある人でさえ答えが見つけられないようなケースに答えるのが、我々のような企業法務の弁護士の仕事です。
とくに新しいビジネスの相談に来るお客様というのは、人のやっていないこと、新しいことをやってお金を稼ごうとしています。そうした方の質問に対しては徹底的に調べてベストの回答を返します。一番あぶなげのないのは「そんなことをしても知りませんよ」という答えなのでしょうが、そんなことをしていたのではお客様に来ていただけません。
また後で"違法だ"と言われても大変です。必要なら役所に相談したり、これまでの判例を調べたりもしますが、最後は自分自身で"ここまでは大丈夫だろう"という判断をします。そういう意味では鼻のきかせ方が必要だということになるし、ある意味リスクを負って判断しているということになります。
 法律というのは基本的に人の営みですから、あるとき突然新しい原則が見つかるということはありません。基本的には、今まであったことの組み合わせです。金融関係でいえば、新しい商品というのはたくさん出てきています。しかしそうした商品も、元々のモデルをひねって新しい商品にしていくのです。本当にひねることができるかどうかは、今ある法律や規制に関係してくるわけです。「そこまでひねってはいけない」というところに引っかかるかどうか、それが問題になってきますし、弁護士の判断が求められます。
法律というのは基本的に人の営みですから、あるとき突然新しい原則が見つかるということはありません。基本的には、今まであったことの組み合わせです。金融関係でいえば、新しい商品というのはたくさん出てきています。しかしそうした商品も、元々のモデルをひねって新しい商品にしていくのです。本当にひねることができるかどうかは、今ある法律や規制に関係してくるわけです。「そこまでひねってはいけない」というところに引っかかるかどうか、それが問題になってきますし、弁護士の判断が求められます。
またそうした判断の元になる判例や先例というのがあり、それを組み合わせたり、積み重ねることで新しい判断ができあがる、判断を広げていくということもあります。それを可能にしていくための能力を常に磨いていなければなりません。それこそがプロフェッショナルとしての証でもあるのです。
もちろんこうした判断も結局は人がやっていることですから、それが世間に受け入れられるかどうか、裁判所に「いいよ」といわれるかどうかは、結局のところつかみきれないものです。だからこそ、世の中の価値観といったものにも常に目配りをしておく必要があります。
これまでの日本社会は、いわゆる村社会だったと思います。日本ではすべてを法律に書いて規定するのではなく、法律には書いていないが人々に共通するルール、暗黙のルールというものがあって、それが法律の代わりになってきていました。
しかし、世界の国々は、それぞれ民族も違う、生い立ちも違う、それぞれ独自に規範のようなものを持っています。グローバル化していくということは、そうした人たちとの接点がどんどん増えていくということです。そうなると村社会ではすまなくなっていきます。
たとえば外資系の金融機関などがやってきて、法律に書かれていなければ暗黙のルールは平気で破ってしまう。お役所が知らない間にめいっぱい儲けてサッと逃げていくことが数多くありました。また契約書を見ても外国は徹底した契約社会ですから、しっかりと書き込みます。日本で作る契約書が3~4ページだとすると、同じ契約内容でもヨーロッパなら15~20ページ、米国なら30~40ページにはなります。グローバルな社会では、こうした現実を受け入れることが必要ですし、これからは欧米のような訴訟社会に近づいていくのかもしれません。
これまで日本は営々と良い物を作って、それを輸出して、しかし、取りぱぐれていました。実は世界には代金を払わないようなやからもいっぱいいるわけです。日本人なら「今日は期日だから借金を返さなければいけない」という感覚になるのでしょうが、「取りに来ないのだから払わなくてもいいだろう」と平気ですませてしまう人々もいます。
私は、湾岸戦争前にイラクへ債権回収の仕事で行ったことがあります。基本的にはイラクの銀行がLC(信用状)を出しているため、それを信じて輸出しているのですが、イラクの銀行がそれを履行しない。金を払ってくれないわけです。債権だけで1兆円ほどあったと思います。
それでイラクが輸出した石油代金の支払いを貯めて、そこから日本の商品の代金を相殺するオイルスキームをつくりました。実は先進国間でパリクラブの協定があって、そういうことはできないことになっていたのです。ところが、私たちが交渉に行ってみれば、前にはドイツがいる、後ろではカナダが待っているというぐあいに、みんな同じ方法でやっているわけですよ。そうした社会であるということも知っておく必要はあると思います。
 これからの法律家、特に企業法務に関わる弁護士の方々には、日本の法律に通じているだけでなく、英米をはじめその他の外国法も勉強してもらいたいと思っています。
これからの法律家、特に企業法務に関わる弁護士の方々には、日本の法律に通じているだけでなく、英米をはじめその他の外国法も勉強してもらいたいと思っています。
また日本のマーケットに対応するため、日本にも海外からたくさんの弁護士がやってきています。日本や東京というマーケットを使ってプレーをしているわけです。彼らは本来なら日本人の弁護士がやるべき分野を手がけているのです。日本のユーザー、たとえば政府機関や企業にも、"日本の弁護士にはできない"という先入観があって、外国の弁護士に依頼しているケースも多いのです。
本来なら日本の権益、利益、最終的には日本で税金を払ってくれている人たちの利益になるような仕事というものは、日本人の弁護士がやるべきだと思っています。新しく弁護士になる方々には、そうした分野にも積極的に挑戦してもらいたいし、そうした仕事に挑戦していくことが私自身の今後の課題だとも思っています。